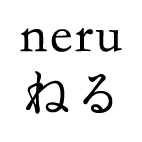企画者〈ねるneru〉は、佃七緒(作家/陶芸・現代美術)、庄子萌(研究者/パフォーミングアーツ)の2名による、アートイベントの企画を通して「鑑賞」について策を練るユニットです。
2024年度は、神戸・岡本にあるアートセンターのOAG Art Center Kobeにて、公募にて決定した、美術・工芸・パフォーマンス・詩などの8名の作家・アート関係者と共に《実験会》という「鑑賞の場の試作とディスカッション」のイベントを、半年に渡り開催してきました。
2025年2-3月には、その《実験会》で得た知見を元に、より広くご覧いただける鑑賞のイベントを開催いたします。
佃七緒
私はこれまで、一人の作家として新作の個展をするときには(全力では)試しきれない、「作品の一部でもあるけど周辺でもあること」がずっと気になってきました。
会場周辺の道のりや、会場で目にするテキストの形態やタイミング、作品にどんな身体の動きで出会うのか、作品空間でどれくらい時間を過ごすのか、作家は作品とともにいるのか/ いないのか、作品が販売されない場合に(何にお金が支払われて/支払われないで)何を来場者は持って帰るのか、などなどです。私は、自身の作品の性質上、これらのことを考えることがとても必要だと感じるとともに、アートをアート関係者・理解者の中だけでの楽しみに留めないためのだいじな工夫の余地でもあると思ってきました。
近年、作家によってはこれらのことを作品の一部として設計したり、作家・開催者がデザイナーやインストーラーの方に依頼をしたりすることも多いと思います。ただ、個人の作家がふと、「前までそこは作品制作とはあまり思ってなかったけど、実は自分の作品にはわりと必要かも…?」となったとき、どこからどうやって始められるのだろうか。
そういったことを、大きな場所もお金もなくても、関心のある人たちと実践的に試作と鑑賞を繰り返しながら検討し合おう、というのが私にとっての〈ねるneru〉企画での活動です。(協働する庄子さんにはまた別の目的や関心があり、ぶつかったりすり合わせたりしながら進めてきました。)
本イベントはこの1 年の「こう始めてみようかな」の蓄積の結果であり総決算です。参加者のみなさんとどう話し合うかというところから鑑賞空間づくりは始まり、今もまだ鋭意準備中です。
ぜひご覧いただきたいです。
少し駅から歩きますが、どうぞ神戸・岡本までお越しください。

浅倉由輝[あさくら ゆき]
1994年大阪府生まれ。2019年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻漆工分野修了。日常で触れた情景、何かをゆっくり待つ時間、緊張をほぐすような空気を込めた作品を制作している。自然物・古物を素材に用い、漆の透明な艶を塗り重ねることでこうした奥行きの表現を試みている。
【近年の活動】
2023 漆と染めを用いたワークショップ「ランドスケープのつづき」(ノランナラン・タローハウス/京都)
2022 舞台美術制作「劇団三毛猫座『くじらの昇る海底』 」(THEATRE E9 KYOTO/京都)
2022 グループ展「ふきよせ – 陶と木と漆のあるくらし -」(なかの邸/京都)
2021 グループ展 「川で交わるつながる繕う」(高瀬川・四季 AIR)
Instagram: @s.a_yuki
諏訪七海 [すわ ななみ]
俳優。京都市在住。
京都造形芸術大学(現京都芸術大学)舞台芸術学科卒業。
たかすか まさゆき
1989年、愛媛県生まれ。東京都在住。まちに佇んだり、土地を歩いたりして、詩を書いたり、ことばをスケッチしたりしている。
【主な活動】
「まちに佇む」
Instagram: @standing_in_the_town
2024 第一詩集『
2020~「RAU 都市と芸術の応答体」メンバー。映像作品などを制作。
主な上映作品:
『スイングビル10階』(2021)、『輪/

むらたちひろ
1986年京都生まれ。2011年京都市立芸術大学大学院美術研究科(染織)修了。「染まる現象 / 染める行為」に内包される様々な「揺らぎ」に身近な世界をうつし見る。
おもな展覧会に、「染・清流館コレクション展 染色の抽象表現」(2024, 染・清流館 / 京都)、「京都府新鋭選抜展」(2023, 京都文化博物館)、 「VOCA展2022」(2022, 上野の森美術館 / 東京)、「TOKAS Emerging 2022」(2022, トーキョーアーツアンドスペース本郷 / 東京)、個展「beyond」(2022, Gallery PARC / 京都)など。
現在、京都・大阪を拠点に活動。
web: murata-chihiro.tumblr.com
Instagram: @chihiro_murata
森絵実子[もり えみこ]
2008年京都市立芸術大学大学院美術研究科染織専攻修了。描きたいモチーフや扱う布の様相に応じて、染色の様々な技法を使い制作を行う
出産を機に、2021年からKomierimoの屋号での商品展開もはじめる。
【近年の活動】
2021~ komierimo名義での展示など(ikke/京都)
2017 “Wafting II – Work With Dye Techniques” (MEDIALIA Gallery / New York)
2016 琳派400年記念京に生きる琳派の美現代作家 200人による日本画・工芸展」(京都文化博物館 / 京都)(日本橋高島屋 8階ホール / 東京)
2015 「琳派400年記念 新鋭選抜展~琳派の伝統から、RINPA の創造へ」(京都文化博物館 / 京都)
2014 「第35回京都美術工芸作家協会展」京都府知事賞受賞(京都)
2007 “International Art Exhibition Summer Pleasures” (A-forest Gallery / New York)
Instagram:@komierimo
山田沙奈恵[やまだ さなえ]
美術家。東京都を拠点に活動。
フィールドワークを中心とした取材によって人間と自然環境の関係性をひもとく映像作品を制作する。自然の脅威と共に暮らすことや、脅威に向かう観光の眼差しなど、ときに矛盾をも含む多重の視点をとらえることを目指す。
国内外の展覧会をはじめ、映画祭等にも参加。主な個展に《山田沙奈恵展 トポフィリア》(富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館、群馬、2023)、《TOKAS-Emerging 2022》(トーキョーアーツアンドスペース本郷、東京、2022)など。
website: sanaeyamada.com
Instagram: @sanae__yamada
吉浦嘉玲[よしうら かい]
事物と、それらが置かれた状況による《事物がただそこにある様相》を映すことを、試みています。
近年は五種のシリーズ作品として、版画、陳列棚、写真、図案、建築模型、茶棚をメディウムとしたオブジェクトを制作。それら作品や ( 鑑賞者を含む ) 他者の「細部」が、ある量感・温度を持ち漂うような空間の設計を、『部屋』という語をとっかかりに試行しています。
経歴など:
京都在住。2019年 Royal College of Art、MA Sculpture 修了(ロンドン、イギリス)。主な活動歴として ”「一般公開」” (ツー・バウンス、佐賀、2023)、個展 ” それぞれの部屋、凝らしの細部・呼吸の熱” (Taro house、京都、2023 )、 “廻覧会” (回様う 現: 四三館、大阪、2021-2022)
website: kaiyoshiura.com
Instagram: @kai_yoshiura
米川幸リオン [よねかわ こう りおん]
1993年生まれ。三重県鈴鹿市出身、京都市在住。
和田ながら[わだ ながら]
演出家。したため主宰。京都在住。
演技という行為に強い関心を持ち、テキストやモチーフを接写するように読み解いていくことで作品ごとに固有の演技の文法の構築をめざす。美術、建築、音楽など様々な領域のアーティストとの共同制作も多数。
主な作品に、多和田葉子の小説を上演した『文字移植』、妊娠・出産を未経験者たちが演じる『擬娩』など。
2018年より多角的アートスペースUrBANGUILDブッキングスタッフ。
website: shitatame.blogspot.com
Instagram: @shitatame
パフォーミングアーツの研究を行う庄子萌、現代美術の制作・企画を行う佃七緒のアーティスト・リサーチユニット。美術等の展覧会や演劇・パフォーマンス等の鑑賞時に、鑑賞者が「どのように作品と時間を過ごす(または過ごさない)か」を中心に、アートの企画の設計を研究・試行する。
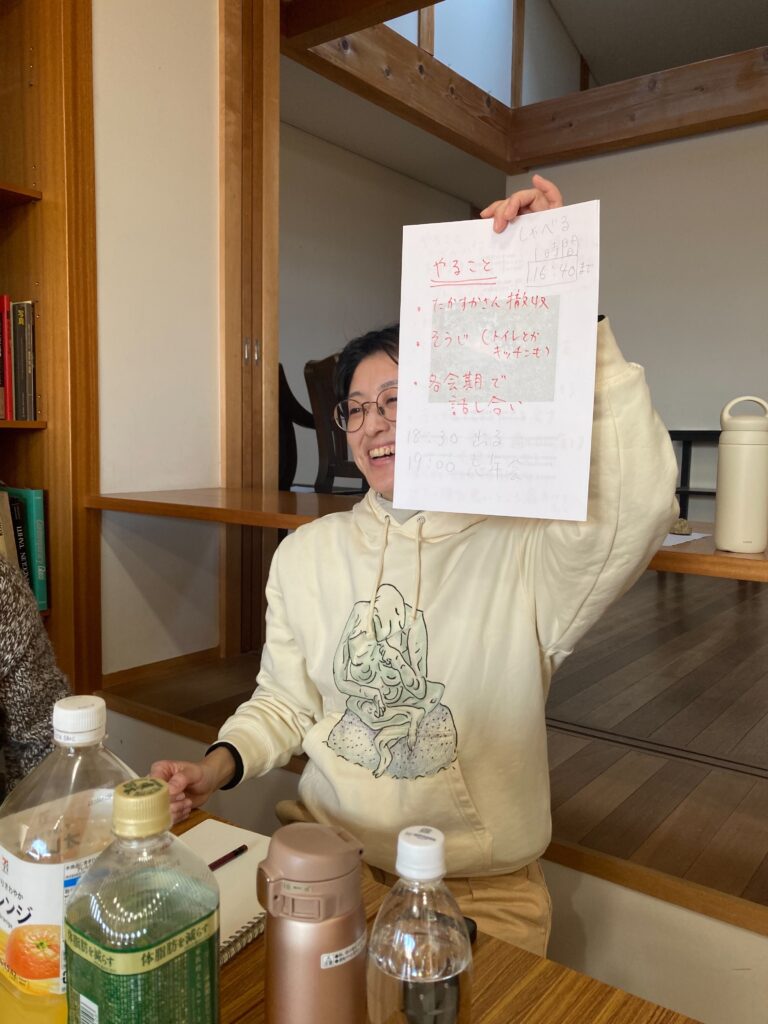
2009年京都大学文学部倫理学専修卒業、2015年京都市立芸術大学大学院美術研究科(陶磁器)修了。国内外に滞在し、他者の日常にて行われる周囲の環境や状況への「カスタマイズ」を抜き出し、陶や布、写真、映像などを用いて表現している。近年の活動に、個展「地のレ展」(NIHA / 京都 / 2023)、La Wayaka Currentでの滞在制作(アタカマ砂漠・チリ / 2023)、「RAU 都市と芸術の応答体」に参加(黄金町・神奈川 / 2022)、京都 HAPS での企画『翻訳するディスタンシング』資料集出版(2022)、など。
website: nanaotsukuda.com
Instagram: @tsukuda70

2008 年京都大学文学部文献文化学専攻フランス語学フランス文学専修卒業。2010 年京都大学文学研究科修士課程 文献文化学専攻英語学英米文学専修修了。2010 年より渡英、シェフィールド大学にて演劇パフォーマンス研究の分野で2011 年に修士号、2021 年に博士号取得。2022 年より立命館大学国際教育推進機構所属、2024 年より准教授。
ものの《あわい》にあるもの、そこで起こる事柄に深い関心を抱き、パラテクストの概念を応用した、パフォーマンス作品およびパフォーマンス・フェスティバルの分析を目下の研究テーマとしている。実践と交わる研究を目指しており、企画者としては、One-to-One performance を中心に扱ったWROUGHT Festival ( 英国シェフィールド/2014, 2016)の共同制作を手がけた。
研究活動と並んで翻訳も行うほか、現在は演劇や翻訳と同様にパフォーマティブな営みである言語教育への関心も深めているところ。
・2024 年度公益財団法人小笠原敏晶記念財団(調査・研究等への助成)採択事業
・本研究はJSPS 科研費(研究課題 “Paratexts and Cross-textual Encounters in Performance Festival Environment”)課題ID:23794351 の助成を受けたものです